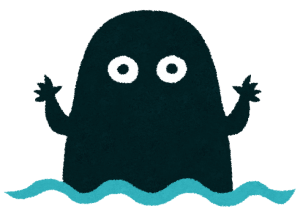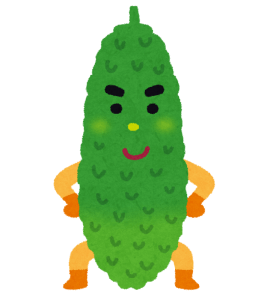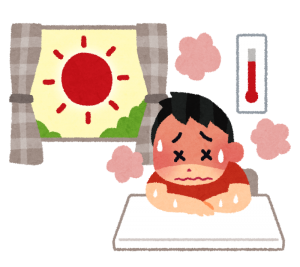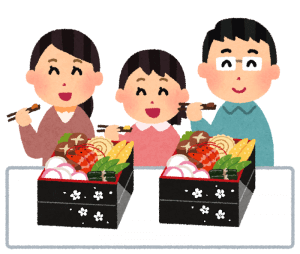皆さんは、お盆にお供えはなさっていますか?
近年は、あまり見かけなくなりましたよね。
お墓参りは、家族そろって行くのでしょうか?
今回は、お盆のお供えの意味や
供えられるお膳、お菓子について、
いっしょに見直してみましょう。
お盆のお供えの意味
お盆のお供えには、何か意味があるんだろうと、
なんとなくは思っていても、
詳しいことはわからないというのが一般的ですよね。
まず気になるのは、
きゅうりの馬となすの牛ですよね。
よく聞くのは、
きゅうりの馬に乗って、
ご先祖様がやってくる。
なすの牛に乗って
ご先祖様が帰ってゆく。
というお話しですよね。
来る時は早く、帰るときはゆっくり、
という意味が込められています。
ただ、このお盆のお供えの意味は、
少し違う地域もあります。
ご先祖様は馬に乗って、
荷物を牛に引かせるという言い伝えもあるようです。
精霊馬(しょうりょううま)と呼ぶのは、
同じみたいですね。
精霊馬を供えるのは、
仏壇ではなく盆棚(精霊棚)になります。
結界として、笹竹を四方に立てて縄を張って、
盆棚を作ります。
毎日、仏壇に手を合わせるのは供養です。
ご先祖様が帰ってくるのは、
お盆だけなのです。
だから特別に、
盆棚を作って、お供えをするんですね。
お膳の内容は?
お盆のお供えで知っておきたいのは、
お膳の決まりですね。
ご先祖様を御もてなしする大事なものです。
毎日、仏壇にお供えするお膳は、、
その日に家族が食べるメニューと同じものを供えます。
お盆では、法事と同じように、「霊供膳」として、
ご先祖様を精進料理で御もてなしをします。
肉、魚はダメなんですね。
お供えは、
きゅうりとなすの精霊馬と同じように、
仏壇ではなく、盆棚になります。
盆棚は、仏壇の前に机を置いて、
その上にクロスやござを敷くことで、
盆棚に見立てることもできます。
きちんと作るのであれば、
先ほども少し説明しましたが、
はじめに、真菰(まこも)を敷いた祭壇を設けて、
四隅に葉っぱのついた笹竹を立てます。
次に、竹の上部にしめ縄を張って、
結界を作ります。
盆棚は、お膳をお供えするために、
必要な置き場所となるのです。
お膳の内容は、
1種類の汁物と5品のおかずとなります。
お盆の期間は、
1日3回お供えするのが習わしですが、
せめて、お盆期間中に一度、みんなで、
ご先祖様を御もてなしできればいいですね。
お菓子は何でもいいの?
お盆のお供えには、お菓子もあります。
自宅で供えるものだけではなく、
訪問先に持っていくものもあります。
どのような選び方をしているか?
ご存知ですか?
昔から、よく見かけるのは、
落雁でお花の形に作られたものですよね。
最近では、
あとで、食べることを考えて、
日持ちするものを選ぶ人が
多くなってきています。
しきたりで言えば、包装したままではなく、
すぐに食べられる状態にして、
ご先祖様が食べられるように、
配慮するという考え方もあります。
傷みやすい物は、
一定時間お供えをして、
「お下がり」として、
みんなで分けていただきます。
訪問で来てくださったお客様にも、
「お下がり」として、
分ける場合もあるので、
日持ちするものを包装したまま、
お供えすることもあります。
基本的には、ご先祖様を尊重して、
ご先祖様が好きだったお菓子を選ぶというのが、
良いでしょう。
よく、お菓子のお供えには、
「のし」つけるのかという話しが出ますが、
水引きの色をどうするかというのと、混同しているようです。
水引きの色は地域差があります。
「のし」は、右上の羽のような形のものですが、
お祝い事のときにつけるものです。
したがって、掛紙をするというのが良いでしょう。
まとめ
お盆のような、
しきたりを要するものは、
だんだんと簡略化もされてきています。
厳密に言えば、宗派や地域差によって、
かなりの違いもあります。
実際のところは、
家族あるいは親族の中心となる方の判断に、
ゆだねることになるでしょうね。