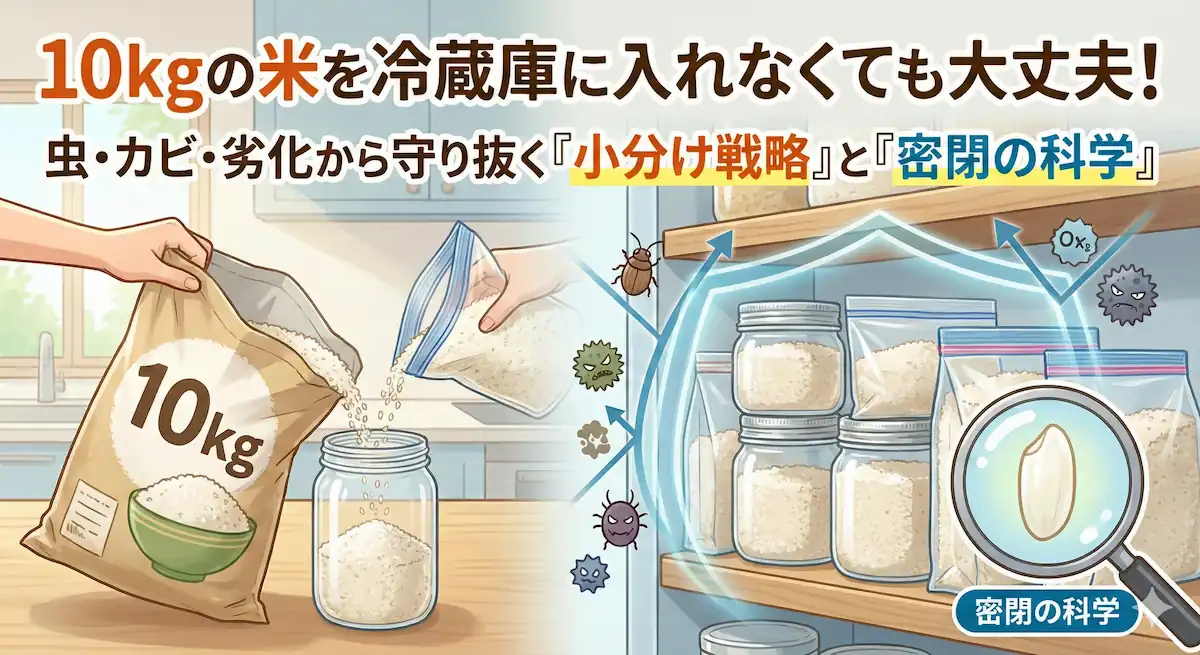おせちと言えば、
お正月にみんなでワイワイ食べるものですよね。
それぞれの料理には縁起が良く意味が込められていますが、
知っている人がだんだん減ってきています。
おじいちゃんおばあちゃんに聞けばすぐに教えてくれますが、
自分の子供とかに聞かれると曖昧しか分からないってことありますよね。
そこで、今回は子供にも分かるようにそれぞれの由来を紹介していきます!
子供と一緒におせち料理の由来を勉強!
そもそもおせち料理の始まりは?
それは、弥生時代のこと。
人々は作物の収穫を季節ごとに神様に感謝し、
生活の節目をつけていました。
自然の恵み、収穫に感謝を込めて神様にお供え物をしていました。
このことを節供と言います。
そしてそのお供え物を料理し、
次の大漁、豊作を願い自然の恵みに感謝して食べていました。
このことを節供料理と言います。
この風習が、今で言うおせち料理の始まりなのです。
時代の流れの中、宮中では元旦や五節句の行事の際に節会(せちえ)と言われる宴が開かれるようになりました。
節会に出される料理をお節会(おせちえ)と呼ばれ、
それが徐々に「おせち」と呼ばれるようになりました。
そして江戸時代の頃に、宮中行事を庶民の生活の中でも取り入れられるようになり、
「今年も新しい1年を無事に迎えることができました。」
と言う感謝を込めて一番大切な節目としてお正月に食べられる料理を
「おせち料理」と呼ばれるようになりました。
おせち料理をお重に詰める意味があった!
それは、「めでたさが重なりますように。」と言う意味が込められていました。
最近では、ネットやお店で作ってもらうことが多くお重のおせち料理を見ることは減りましたが、
ちゃんとした意味があったんですね~。
さらにはこんな理由もあったんです!
それは、場所を取らない!
確かに、重なってる分コンパクトですよね~。
それに昔はラップなんて便利なものがなかったから、
重ねることで虫や湿気の防止のためでもあったんですね。
以上のようにおせち料理とは弥生時代から受け継がれていたんですね!
今後も毎年元旦には、新年を迎えることができたことへの感謝を込めておせち料理を頂きましょう。
おせち料理の数の子の由来は?
数の子はニシンという魚の卵です。
たくさん子供が生まれることから、
数の子を食べることで「子宝に恵まれますように。」という意味が込められています。
おせち料理の黒豆の由来は?
黒豆は、「まめに元気に働く。」という意味が込められています。
毎年黒豆を歳の数ほど食べたりしていますよ♪
黒豆を食べて新年もまめに元気に過ごしましょう!
まとめ
おせち料理と数の子、黒豆の由来を紹介してきましたが、
まだまだ他にも日本ならではの優しい意味が込められています。
おせち料理の一つ一つの意味を感じながら食べると、
少し違う味わいになるかもしれませんよ♪