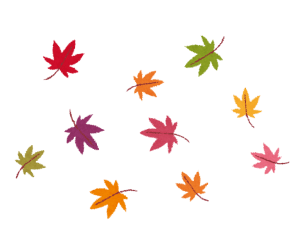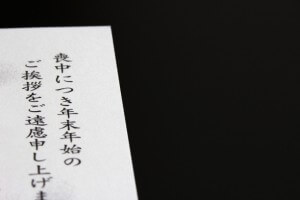喪中はがきとは家族や親族に不幸があった場合に、慶事を避け喪に服すことを知らせ
故人の対する生前の感謝の気持ちと新年の挨拶を欠くことを知らせる挨拶状のことです。
一般的には喪に服する期間は一年とされています。
1章 喪中はがき、故人が複数の場合
一般的には喪中はがきを出す範囲は二親等以内の親族が亡くなった場合とされています。
一親等とは、本人及び配偶者の父母、子供。
二親等とは、本人及び配偶者の兄弟姉妹、兄弟姉妹の配偶者、祖父母、孫を指します。
喪中の間に複数亡くなられている場合はどうすればいいのでしょうか?
故人が複数の場合でも喪中はがきは一枚で出します。
その際亡くなった年齢順ではなく亡くなった月日の早い順に記載します。
2章 喪中はがきの例文。故人が複数の場合
故人が複数の場合の場合は、
◯月(故人続柄) 名前
◯月(故人続柄) 名前
が永眠致しました
のように記します。
この場合は受け取った相手に、「親族の誰が亡くなったのか」・
「夫側の親族か妻側の親族か」など正確に分かる書き方にすることが大切です。
各家庭の事情から故人の名前や年齢を出さずに
「喪中につき年末年始のごあいさつを謹んでご遠慮申し上げます」
という場合もあります。
3章 喪中はがきのマナー。出す時期はいつ?
喪中はがきのマナーとして、出す時期はいつかということがあります。
喪中はがきは年賀欠礼の挨拶状ですので、毎年年賀状の交換をしている方に新年の挨拶をする前つまり年内に届けば問題はありません。
実際は喪中はがきを受け取った側は年賀状を送らないことになっているので11月下旬から12月初旬までに届くようにすると先方に失礼がありません。
また喪中はがきには、
・時候ごあいさつ
・喪に服しているので年賀状が出せないこと
・生前のお付き合いへの感謝
・良い年をお迎え下さい
などの文章が入っていることが望ましいマナーとされています。
まとめ
喪中はがきに関しては各家庭の考え方や地域の特性によってさまざまな違いがあります。
迷ったときは年長者の方に相談するなどして相手にも故人にも失礼のないようにしましょう。